Masakiです。
以前、このブログでは私立小学校について解説しました。
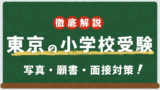
今回は国立小学校について学校一覧・ランキング・地域別解説・受験情報・面接・塾・抽選制度・進学後の生活・保護者の声などを含め解説していきたいと思いますので、最後まで御覧ください。
国立小学校とは?その魅力と特徴
国立小学校とは、全国の国立大学が運営する附属小学校です。
教育学部などをもつ大学の実験校という位置づけで、新しい教育方法の研究や教員の養成の場としての役割を担っています。
そのためカリキュラムにも特色があり、英語やICT教育、アクティブラーニングなど先進的な取り組みが行われていることが多いです。
学費が無料(公立同様)で教育水準が高い点も大きな魅力で、私立小学校に比べ経済的負担が少なく質の高い教育を受けられることから、毎年多くの家庭が入学を志望しています。
また全国から児童が集まるため、多様な背景をもつ友達と交流できる点や、中学校への内部進学制度がある学校が多い点も、国立小学校ならではの特徴です。
全国の国立小学校一覧と所在地
国立小学校は全国に67校あり、原則として各都道府県に1校以上設置されています(大学のキャンパス所在地によっては複数ある地域もあります)。
以下に主な地域ごとに国立小学校の一覧と所在地をまとめます。
各学校名には国立大学名が含まれており、その大学の附属校であることがわかります。
東京都の国立小学校一覧
- お茶の水女子大学附属小学校(東京都文京区)
- 筑波大学附属小学校(東京都文京区)
- 東京学芸大学附属竹早小学校(東京都文京区)
- 東京学芸大学附属世田谷小学校(東京都世田谷区)
- 東京学芸大学附属大泉小学校(東京都練馬区)
- 東京学芸大学附属小金井小学校(東京都小金井市)
大阪府の国立小学校一覧
- 大阪教育大学附属池田小学校(大阪府池田市)
- 大阪教育大学附属天王寺小学校(大阪市天王寺区)
- 大阪教育大学附属平野小学校(大阪市平野区)
京都府の国立小学校一覧
- 京都教育大学附属京都小中学校(京都市)※小中一貫校
- 京都教育大学附属桃山小学校(京都市)
愛知県の国立小学校一覧
- 愛知教育大学附属名古屋小学校(名古屋市)
- 愛知教育大学附属岡崎小学校(岡崎市)
福岡県の国立小学校一覧
- 福岡教育大学附属福岡小学校(福岡市)
- 福岡教育大学附属小倉小学校(北九州市)
- 福岡教育大学附属久留米小学校(久留米市)
その他の地域の国立小学校一覧
- 北海道:北海道教育大学附属札幌小学校(札幌市)、附属旭川小学校(旭川市)、附属函館小学校(函館市)
- 東北地方:弘前大学教育学部附属小学校(青森県弘前市)、岩手大学教育学部附属小学校(岩手県盛岡市)、宮城教育大学附属小学校(宮城県仙台市)、秋田大学教育文化学部附属小学校(秋田県秋田市)、山形大学附属小学校(山形県山形市)、福島大学附属小学校(福島県福島市)
- 関東地方(東京以外):茨城大学教育学部附属小学校(茨城県水戸市)、宇都宮大学共同教育学部附属小学校(栃木県宇都宮市)、群馬大学共同教育学部附属小学校(群馬県前橋市)、埼玉大学教育学部附属小学校(埼玉県さいたま市)、千葉大学教育学部附属小学校(千葉県千葉市)、横浜国立大学教育学部附属横浜小学校(神奈川県横浜市)、横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校(神奈川県鎌倉市)
- 中部地方(愛知以外):新潟大学附属新潟小学校(新潟県新潟市)、新潟大学附属長岡小学校(新潟県長岡市)、富山大学教育学部附属小学校(富山県富山市)、金沢大学附属小学校(石川県金沢市)、福井大学教育学部附属義務教育学校(福井県福井市)※小中一貫、山梨大学教育学部附属小学校(山梨県甲府市)、信州大学教育学部附属長野小学校(長野県長野市)、信州大学教育学部附属松本小学校(長野県松本市)、岐阜大学教育学部附属小中学校(岐阜県岐阜市)※小中一貫、静岡大学教育学部附属静岡小学校(静岡県静岡市)、静岡大学教育学部附属浜松小学校(静岡県浜松市)、三重大学教育学部附属小学校(三重県津市)
- 近畿地方(大阪・京都以外):滋賀大学教育学部附属小学校(滋賀県大津市)、奈良教育大学附属小学校(奈良県奈良市)、奈良女子大学附属小学校(奈良県奈良市)、兵庫教育大学附属小学校(兵庫県加東市)、神戸大学附属小学校(兵庫県神戸市)、和歌山大学教育学部附属小学校(和歌山県和歌山市)
- 中国・四国地方:鳥取大学附属小学校(鳥取県鳥取市)、島根大学教育学部附属小学校(島根県松江市)※現在募集停止中の場合あり、岡山大学附属小学校(岡山県岡山市)、広島大学附属小学校(広島県東広島市)、広島大学附属東雲小学校(広島県広島市)、広島大学附属三原小学校(広島県三原市)、山口大学教育学部附属山口小学校(山口県山口市)、山口大学教育学部附属光義務教育学校(山口県光市)※小中一貫、徳島大学附属小学校(徳島県徳島市)、鳴門教育大学附属小学校(徳島県鳴門市)、香川大学教育学部附属高松小学校(香川県高松市)、香川大学教育学部附属坂出小学校(香川県坂出市)、愛媛大学教育学部附属小学校(愛媛県松山市)、高知大学教育学部附属小学校(高知県高知市)
- 九州・沖縄地方(福岡以外):佐賀大学教育学部附属小学校(佐賀県佐賀市)、長崎大学教育学部附属小学校(長崎県長崎市)、熊本大学教育学部附属小学校(熊本県熊本市)、大分大学教育学部附属小学校(大分県大分市)、宮崎大学教育学部附属小学校(宮崎県宮崎市)、鹿児島大学教育学部附属小学校(鹿児島県鹿児島市)、琉球大学教育学部附属小学校(沖縄県宜野湾市)
※上記のとおり、一部の国立小学校は**小中一貫校(義務教育学校や併設型)**になっており、小学校と中学校が一体となっています。
地域別の国立小学校人気ランキングと偏差値傾向
国立小学校は基本的に入学試験(考査)の点数による合否判定だけでなく抽選も介在するため、私立のような明確な「偏差値」はありません。
しかし、受験者数や系列中学校(内部進学先)の難易度などから、学校ごとの難易度の目安が語られることがあります。
地域別に見ると、首都圏や京阪神の国立小学校は特に高い人気と難易度を誇ります。
首都圏(関東)では、東京都内の附属小学校(筑波大附属小、お茶の水女子大附属小、東京学芸大附属各校など)が定員に対し応募者数が非常に多く、事前抽選通過だけでも狭き門です。
これらは系列の附属中学校や高等学校も難関校として知られており、小学校受験の難易度もトップクラスと言われます。
神奈川県の横浜国立大学附属(横浜小・鎌倉小)や千葉大学附属小学校、埼玉大学附属小学校なども首都圏で人気が高いです。
偏差値の指標で言えば首都圏国立小は概ね60前後~70近くと私立名門小学校に匹敵する難易度とされます(あくまで目安)。
実際の競争率も後述するように50倍前後になる学校があり、非常に狭き門です。
関西圏では、大阪教育大学附属の池田・天王寺・平野小学校の3校がいずれも高い人気があります。
特に池田小学校は系列中学校の実績もあり難易度が高い傾向です。京都府の京都教育大学附属京都小中学校および附属桃山小学校の2校も難関で、偏差値換算では65~70前後とも言われます。
奈良県では奈良女子大学附属小学校が高い難易度(同附属中等教育学校への内部進学も可能)で、奈良教育大学附属小学校とともに人気です。
兵庫県では神戸大学附属小学校が有名で、こちらも内部進学先の中等教育学校が難関校のため高い競争率です。
関西の国立小学校全体として、偏差値目安は50台後半から60台に位置し、やはり高いレベルと言えます。
その他の地域でも、各地方の国立小学校はその地域では有数の人気校です。
例えば愛知県の愛知教育大附属小(名古屋・岡崎)は地元で難関とされますし、九州では福岡教育大学附属小各校(福岡・小倉・久留米)が高倍率で知られます。
地方では首都圏ほど倍率が極端に高くない場合もありますが、それでも志願者は定員の10倍以上になることが一般的で、偏差値に換算すれば50前後から60程度の難易度と見られます。
ランキングとしての序列は年によって変動しますが、概ね「都市部の附属小学校ほど難しい」傾向があります。
なお、小学校受験専門の模試主催会社などが独自に推定した偏差値表を公開することもありますが、国立小学校の場合は抽選要素が大きいため参考程度に捉えるとよいでしょう。
抽選と面接の仕組み・倍率・スケジュール
国立小学校の入試は、私立小学校とは大きく異なり「抽選」による選抜が行われる点が特徴です。
応募者数が定員を大幅に上回るため、公平性を保ちつつ受験者数を絞る目的で抽選が導入されています。
抽選のタイミングや回数は学校によって様々ですが、大きく分けて以下のパターンがあります。
出願後の事前抽選(一次選考)
願書を出した全応募者を対象に、まず入学考査(試験)を受けられる人数まで無作為抽選で絞り込みます。
定員の数十倍もの志願者がいる都市部の附属小などで採用される方式です。
この抽選に外れると試験を受けること自体ができず、不合格となります。
試験・面接後の抽選(二次選考)
学力検査や行動観察、親子面接などの考査を経て合格候補となった児童の中から、最終的な合格者を抽選で決定します。
試験の成績や面接評価が優秀でも、抽選で漏れて不合格になるケースがあるため、運の要素が最後まで残ります。
学校によっては二段階抽選を行うところもあります。
例えば東京都内や大阪府内の人気校では、「事前抽選」→「試験・面接」→「最終抽選」と計2回の抽選を経て合格者を決める仕組みです。
いずれにせよ、私立のように純粋な成績順では合否が決まらないため、「どんなに準備しても抽選で涙をのむ可能性がある」のが国立小学校受験の難しいところです。
倍率(競争率)も非常に高く、都市部では驚くほどの数字になります。人気校では志願者数が定員の50~70倍に達する年もあります。
例えば東京学芸大学附属小金井小学校では男女別で60倍前後、筑波大学附属小やお茶の水女子大学附属小学校でも数十倍規模の高倍率です。
大阪教育大学附属池田小学校など関西の有名校も20~30倍以上になることが珍しくありません。
地方の附属小学校でもおおむね10倍以上、平均すると15~20倍程度の倍率となります。抽選による絞り込みがあるとはいえ、それだけ多くの志願者が国立小学校を目指していることがわかります。
スケジュール(日程)は各校で若干異なりますが、多くの国立小学校は秋から冬にかけて選考が行われます。
願書受付が9月から11月頃、抽選や考査(試験・面接)が11月末から1月頃、合格発表が1月中~下旬という日程が一般的です。
例えば首都圏の国立小は説明会が夏から秋にあり、願書出願は10月下旬、抽選→筆記・行動観察等の考査が11~12月、合格発表は12月末から1月初旬という流れが多いです。
関西も大阪や兵庫では概ね願書10月、試験と面接が12月末~1月といったスケジュールです。
ただし一部例外もあります。
奈良県では奈良教育大学附属小学校が願書提出・抽選・面接を全て9月中に行い、非常に早い段階で合否が決定します。
奈良女子大学附属小学校も出願が9月、考査と面接が10月と他地域より前倒しです。
京都府では桃山小学校のみ願書が7月提出・考査が8月と早く、附属京都小中学校は他地域並みの11月出願・1月考査となっています。
国立小学校は私立に比べ出願時期が遅め(秋冬)と言われますが、このように地域によって多少ズレがあります。
併願予定の場合は各校の募集要項を早めに確認し、日程が重ならないよう注意が必要です。
国立小学校の受験対策:塾・模試・願書・服装・親の面接準備
国立小学校に合格するためには、早めの受験対策と綿密な準備が欠かせません。
抽選の運任せな部分もありますが、実際には考査(筆記・行動観察・面接など)で一定の基準を満たさなければ抽選に進めない、あるいは抽選に通っても試験で評価されなければ合格できません。
ここでは塾や模擬試験の活用から願書・面接準備まで、主な対策ポイントを解説します。
幼児教室や模擬試験の活用
国立小学校を目指す家庭の多くは、小学校受験専門の幼児教室や塾に通って対策しています。
私立小受験との併願者も多いため、基本的なペーパー試験対策や行動観察の練習、巧緻性(手先の器用さ)・運動テスト対策などは幼児教室で指導を受けるケースが一般的です。
国立小独自の傾向にも対応したカリキュラムを持つ塾もあるので、情報収集に努めましょう。
また、志望校対策として模擬試験(模試)を受けることも有効です。
大手幼児教室や受験情報サイト主催で、国立小学校受験向けの模試や親子面接練習会が開催されることがあります。
模試を通じてお子さんの現状レベルや課題を把握し、本番までに弱点を補強すると安心です。
ただし、小学校受験では学力一辺倒ではなく生活習慣や行動面も見られるため、ご家庭でも自立心や協調性を養う教育を心がけましょう。
願書の書き方と提出準備
願書(出願書類)の準備も極めて重要です。
国立小学校の願書では、保護者が家庭での教育方針やお子さんの長所・短所、志望理由などを書く欄があります。
これらは面接での質問につながるため、学校の教育理念と照らし合わせつつ一貫性のある内容を心掛けます。
例えば「自主性を尊重する校風」に対し「家庭でも自主性を伸ばす取り組みをしている」等、学校側が求める家庭像にマッチするエピソードを盛り込むと良いでしょう。
願書は書き方のマナー(黒のペンで丁寧な字で書く、修正液を使わない等)にも注意が必要です。
下書きを十分行い、塾の先生など第三者の添削を受けると安心です。
また提出期限や必要書類も要チェックです。国立小学校の場合、願書提出時に検定料(受験料)の振り込み証明書を添付する必要があります。
検定料はおよそ2,000〜3,000円程度ですが、一次と二次で分けて支払う学校もありますので募集要項を確認してください。
提出方法は郵送指定の学校が多いですが、持参の場合も服装等に気を配りましょう(願書配布や提出時も保護者の身だしなみを見られているとの意識が大切です)。
試験当日の服装と親の面接対策
試験日・面接日の服装は、受験生本人も保護者も「お受験スタイル」と呼ばれる清楚な服装を用意します。
一般的に紺色系統のスーツが無難で、派手な色柄は避けます。
男児であれば白シャツに紺の半ズボンやスーツ、女児であれば紺のワンピースやジャンパースカートにボレロなどが定番です。
保護者も父親はダークスーツに落ち着いたネクタイ、母親は紺のスーツまたはワンピースに控えめなアクセサリー程度にし、髪型や靴、バッグもシンプルで上品なものを選びます。
幼稚園受験と違い、小学校受験では子どもも制服風のかっちりした装いが多い点が特徴です。
親の面接も国立小学校受験では重視されます。
面接では両親(またはいずれかの保護者)と子どもで臨み、家庭の教育方針や志望理由、子どもの長所短所、普段の家庭学習の様子などについて質問されます。
答えやすそうな質問でも、一貫性や具体性が求められます。
夫婦で回答が食い違わないよう事前に話し合い、想定質問集を作って練習しておきましょう。
特に「本校を志望した理由」「お子さんの家庭での教育で心がけていること」「入学後に親としてどのように関わりたいか」といった定番事項はスムーズに答えられるようにしておきます。
また、子どもの面接対策としては、挨拶や受け答えの練習はもちろんですが、親が口を挟まず自分の言葉で話せるようにしておくことが大切です。
緊張で黙ってしまわないよう、日頃から初対面の大人と話す練習をすると良いでしょう。
面接官(校長先生や教員)が複数いても臆さず受け答えできるよう、家庭でもロールプレイングをするなど準備してください。
親子面接では家庭の雰囲気や教育方針が学校の求めるものと合っているかが見極められますので、願書に書いた内容と矛盾がないよう心掛け、自信と笑顔を持って臨みましょう。
国立小学校入学後の生活:学費・制服・給食・学区制など
晴れて国立小学校に合格し入学すると、その後の学校生活は公立小学校とは似ている部分と異なる部分があります。
ここでは学費や学校指定品、通学面など、入学後の生活面についてまとめます。
学費・諸経費について、国立小学校は授業料・入学金が無料です。
これは義務教育課程であるため、公立小学校と同様に授業料無償の制度が適用されているためです。
ただし学校徴収金や寄付金などは多少かかります。
例えば後援会費や育友会費(PTA会費)、施設維持費などの名目で年数万円程度を負担する学校もあります。
一般には年間10〜30万円程度の諸経費が必要と言われますが、これは給食費や制服代、教材費、遠足や修学旅行費用などすべて含めた概算です。
公立小学校でもこれら実費はかかるため、基本的に国立小だから特別に高額な学費が発生するわけではありません(私立小に比べれば格段に費用負担は軽いです)。
制服・持ち物については、多くの国立小学校で制服(標準服)が指定されています。
デザインは学校によって様々ですが、伝統校ではブレザータイプやセーラー服風など格式あるものが多いです。
入学時に制服一式や通学カバン、体育着、上履きなど指定用品を揃える必要があり、初年度はまとまった出費となります。
制服代だけで数万円、その他体操服や帽子など合わせると合計5〜10万円程度見ておく家庭が多いです。
ただし中には私服通学可で制服のない附属小学校もわずかですが存在します(ごく一部で、大半は制服ありです)。
給食については、国立小学校でも基本的に公立小学校と同様に学校給食が提供されます。
各自治体の公立と同じように栄養バランスのとれたメニューが用意され、保護者は月額数千円程度の給食費を支払います。
国立だからといって特別なメニューになるわけではなく、地域の学校給食センターから配送される場合と、附属学校独自に調理室で作る場合があります。
いずれにせよ栄養管理された給食があり、お弁当不要なのは公立と同じです。
学区制の有無と通学について、公立小学校と大きく異なるのが学区による指定がない点です。
国立小学校は基本的に居住地に関係なく誰でも出願・入学可能です(極端に言えば他府県からの通学も可能)。
そのため通学距離が長くなる子も多く、公共交通機関で電車やバスを乗り継いで通う児童もいます。
低学年のうちは保護者が送迎したり、同じ方面の保護者同士で交代で見送りするケースもあります。
公立のような「集団登校」はないため、安全面に配慮して学校側が登下校時に教職員を配置したり、保護者ボランティアが見守る取り組みをしている学校もあります。
住まいから遠い国立小に進学する場合、保護者の送り迎え負担や交通費がかかる点には留意が必要です。
学校行事や教育方針にも特色があります。
附属小学校では大学の教育研究の一環として研究授業や公開授業が行われることがあります。
全国から教員が参観に訪れる研究発表会では、児童が最先端の授業を受ける機会にも恵まれます。
また英語活動や理科の実験設備の充実、大学施設との連携イベントなど、国立ならではの恵まれた環境も魅力です。
一方で教員の異動サイクルが早く、数年で担任が代わることもあります(大学附属校の教員は研究職・教員養成の兼ね合いで異動が比較的多い傾向があります)。
そのため年度によって授業進度や指導方針が変わることもあり、子どもが慣れるまで戸惑う場合もあります。
保護者は学校からの発信に注意深く耳を傾け、家庭でフォローする姿勢も大切です。
卒業後の進学先とエスカレーター進学の有無
国立小学校を卒業した後、中学校への進路は大きく分けて2通りに分かれます。
ひとつは同じ大学附属の中学校へ内部進学するパターン、もうひとつは外部の中学校を受験するパターンです。
多くの国立小学校には系列の附属中学校が存在し、希望すれば一定数が内部進学できる道があります。
ただしその制度や定員は学校ごとに異なります。
例えば小中一貫校(義務教育学校)として設立されている所では、基本的に全員がエスカレーター式に中等教育過程へ進みます(京都教育大附属京都小中や山口大附属光校などは小1から中3まで在籍)。
一方、附属中学校へ進むには別途選抜試験がある学校も少なくありません。
東京学芸大附属小学校の各校や神戸大附属小学校などでは、小学校からそのまま上がれる人数に上限があり、内部進学試験や成績等による選抜が行われます。
大阪教育大学附属小学校の場合、附属中学校へ進学できない児童も毎年一定数おり、希望者全員が無条件で内部進学できるわけではありません。
このように「エスカレーター式」に中学まで保証されているかどうかは学校によって異なるため、入学前に確認しておく必要があります。
内部進学枠が限られる場合、国立小の在校生も小学校在学中に中学受験(他の私立や国公立中高一貫校を受験)をするケースが多いです。
実際、筑波大学附属小など難関国立小の児童は、小学校卒業後に他の難関私立中学へ合格する例も珍しくありません。
これは国立小で培った学力や自主性を生かしつつ、更に上位の進学先を目指す家庭があるためです。
逆に内部進学制度が充実している附属小(例えば奈良女子大附属小→附属中等教育学校など)では、大半の児童がそのまま系列中学・高校へ進む傾向があります。
高校進学まで見据えると、附属中学校から更に附属高校へ進める学校もあります。
筑波大学附属中学校から附属高校へ、横浜国大附属中学から附属横浜高校へ、といったように中高一貫に近い形でエスカレーター進学可能な大学附属も存在します。
ただし高校段階になると受験で外部進学する生徒も多く、一概に全員がそのまま大学附属高校へ行くとは限りません。
まとめると、国立小学校は小学校段階ではゴールではなく通過点であり、その後の進路選択肢が広がる環境と言えます。
中学からはさらに選抜が行われるケースが多いため、小学校入学後も油断せず学習を積み重ねていくことが大切です。
内部進学できなかった場合でも、国立小での6年間で培った基礎学力や自主性は中学受験に役立つでしょう。
国立小学校に関するよくある質問
Q. 国立小学校の受験に向いているのはどんな子?
A. 一般的に「落ち着いていて指示行動がとれる子」「好奇心旺盛で色々なことに挑戦できる子」が向いていると言われます。
国立小の考査では知能テスト的な問題だけでなく行動観察(集団での遊びや課題活動)が重視されます。
他のお子さんと協力できる協調性、自分の考えを発言できる積極性があると有利です。
また抽選を突破する運も必要ですが、それ以前に基本的な生活習慣(挨拶や受け答え、椅子にきちんと座れる等)が身についていることが前提となります。
Q. 親はどのような準備をすれば良いですか?
A. お子さんの受験勉強をサポートすることはもちろんですが、親としての面接対策や情報収集も重要です。
夫婦で教育方針をよく話し合い、志望校の校風に合った受け答えができるよう準備しましょう。
また学校説明会や願書配布日に積極的に参加し、最新の入試情報を入手してください。願書の書き方や面接マナーについては幼児教室の講座や書籍も参考になります。
さらに、日頃から家庭でニュースや本に触れさせたり博物館に行くなど、家庭教育の充実も心がけると良いでしょう。
「家庭でどんな教育をしていますか?」という質問に具体例をもって答えられるようにしておくと安心です。
Q. 国立小学校のデメリットはありますか?
A. 人気が高い国立小ですが、いくつか留意すべき点もあります。
まず入学までのハードルが高い(抽選があり不確実)ため、受験準備に労力をかけても入れないリスクがあります。
次に通学距離が長くなりがちで、小学校から電車通学になる子も多いです。
その分、時間的・体力的負担がかかったり、保護者の送り迎えの手間がかかる場合もあります。
また地元の友達ができにくいという側面もあります。
地域の公立小学校に通っていれば近所の友人ができますが、国立小では各地から集まるため放課後に遊ぶ友達が遠方在住というケースもあります。
さらに教育面では、先述の通り教員の異動が多く授業の進度やスタイルが変わりやすいことや、公立に比べカリキュラムが柔軟な分、中学受験向けの勉強計画は家庭で立てる必要があることが挙げられます。
こうしたデメリットも踏まえ、それでも魅力が上回るかを各家庭で検討すると良いでしょう。
まとめと注意点
国立小学校について、その概要から受験対策、入学後の生活まで網羅して説明しました。
学費がかからず高度な教育環境を得られる国立小学校は大変魅力的ですが、その分入学までの競争は非常に激しく、運や家庭の努力も求められます。
受験準備を進める中で最新の情報収集を怠らず、志望校の傾向に合わせた対策を心がけてください。
記事内では普遍的な情報を中心に記載しましたが、実際の募集要項や選考方法は各年度で変更される可能性があります。
特に募集人員やスケジュール、内部進学の制度などは最新の公式発表を確認するようにしてください。
合格後も油断せず、引き続きお子さんの成長を支えていくことが大切です。
国立小学校は「入って終わり」ではなく、その後の成長を大きく広げてくれる舞台です。
受験に挑戦する過程自体がお子さんの糧になります。
ご家庭で十分に話し合い、メリット・デメリットを理解した上で準備を進めれば、きっと実りある結果につながるでしょう。
国立小学校受験を検討するすべてのご家庭にとって、本記事の情報がお役に立てば幸いです。
関連記事を読むことで子供の教育のさらに深い知識を知ることができます。

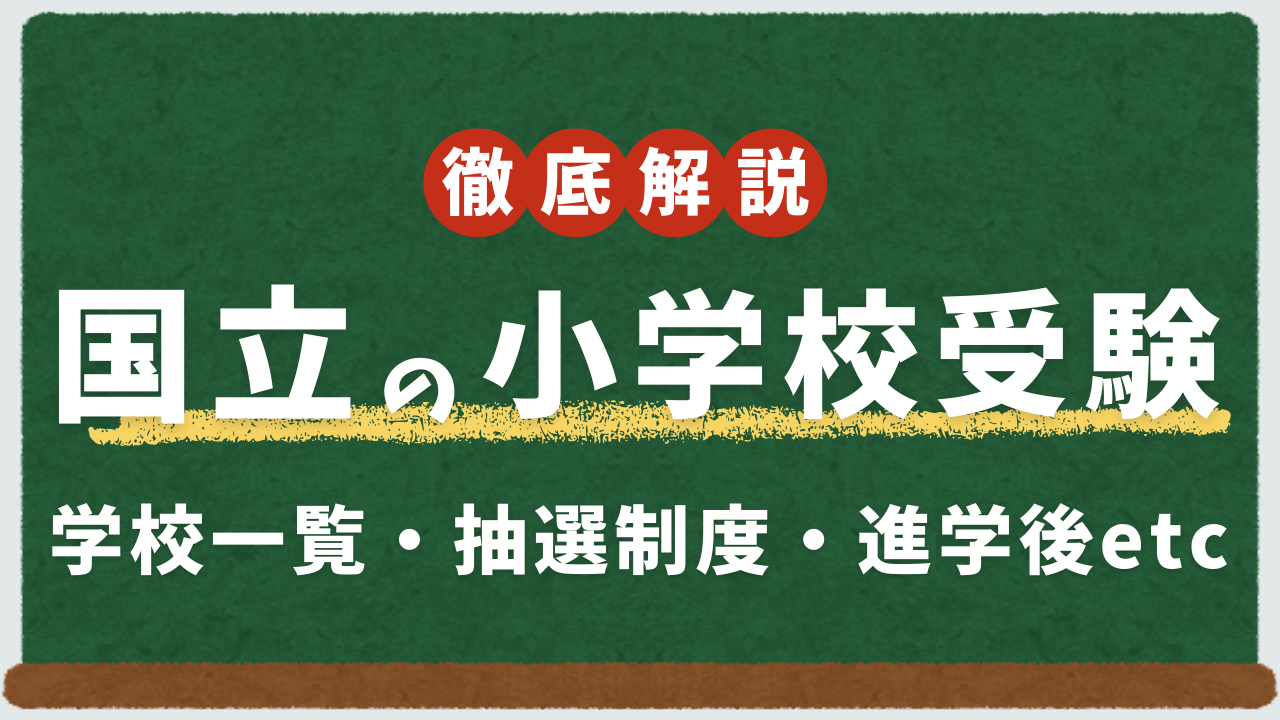
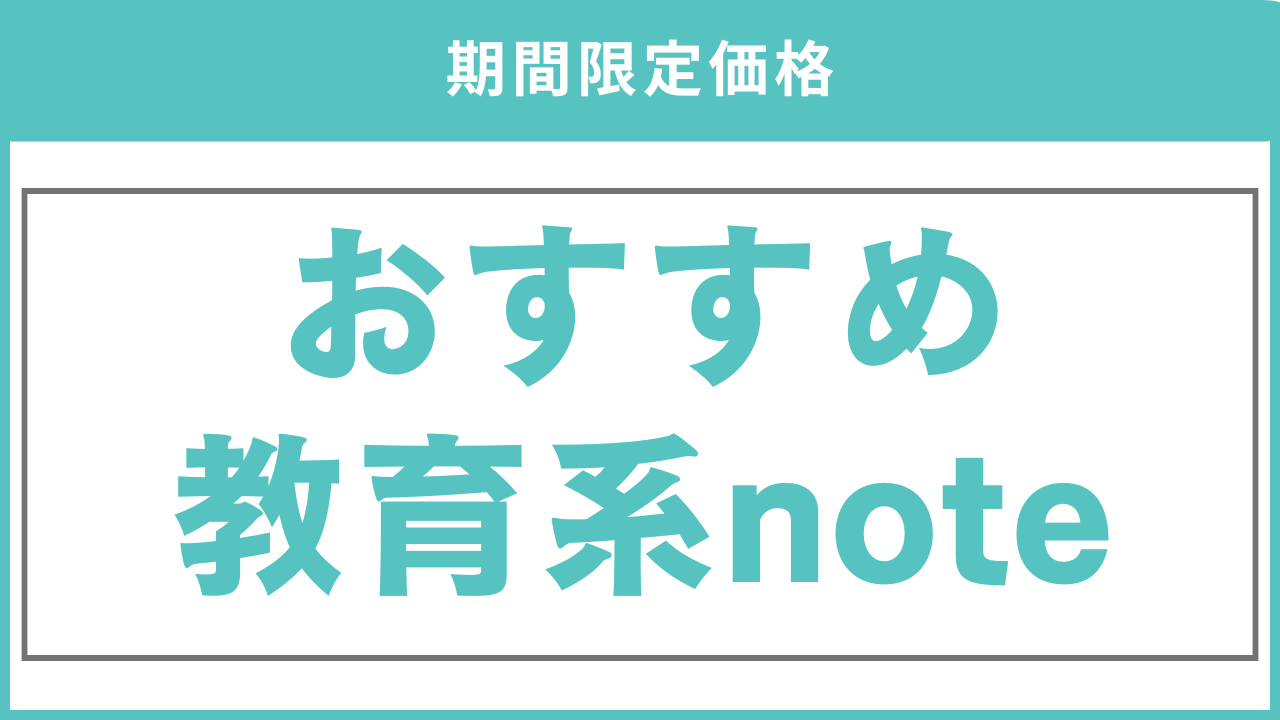


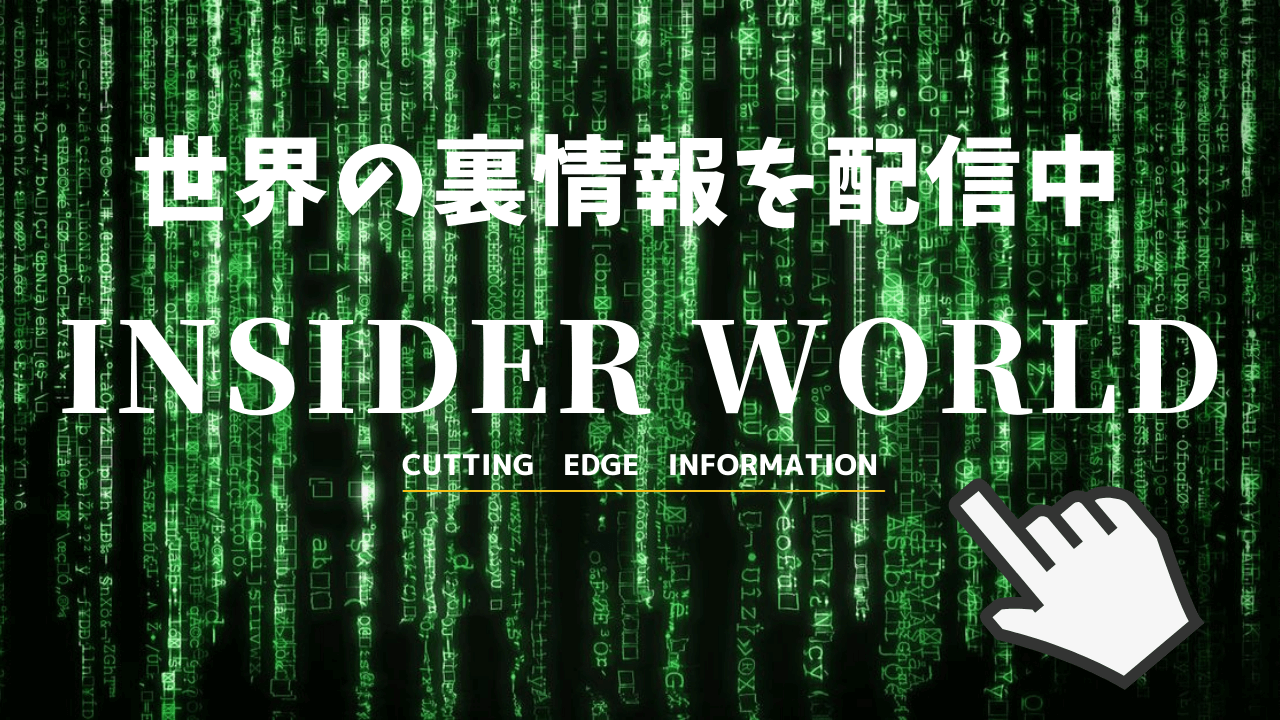
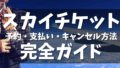
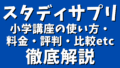
コメント