Masakiです。
東京の小学校受験では、合格発表の日が親子にとって最も緊張する山場となります。
そもそも小学校受験は全国平均では志願者わずか約2%ですが、東京都に限ると約5%といわれ、首都圏では多くのご家庭がチャレンジしています。
競争率の高い東京の小学校受験で後悔しないために、何を準備し、どう臨めば良いのでしょうか。
本記事では「東京の小学校受験で合格」に向けてで失敗しないためのポイントを、専門家のアドバイスや公式情報も交えつつ、写真撮影・願書準備・面接対策まで総合的に解説します。
最後まで読めば、小学校受験に向けた悩みが解消され、自信を持って本番に臨めるはずです。
小学校受験の合格発表はいつ?日程と確認方法【東京エリア】
東京エリアの小学校受験の合格発表時期は主に11月上旬~中旬です。
東京都内の私立小学校では試験(考査)が10月末~11月初旬に集中し、合格発表は試験当日~翌日となるケースが大半です。
たとえば11月1日に試験を実施する学校では、11月2日朝に結果通知が行われる場合があります。
一方、国立小学校(附属小)の合格発表は私立より遅く、11月下旬~12月上旬になる傾向があります。
国立は抽選や一次選考を経て最終合格者を決定するため、結果通知が段階的に行われます。
合格発表の確認方法は、学校によって以下のパターンが見られます。
・校内掲示:学校の正門や掲示板に受験番号を掲示する方法です。指定時間に学校へ向かう必要があるため、時間厳守が求められます。
・Web発表:学校専用の合否確認サイトに、受験票に記載されたIDやQRコードを用いてアクセスする形式です。自宅で確認できるため便利ですが、アクセス可能時間に制限がある場合が多いです(例:○○小学校は試験翌日9:00~当日23:59まで)。
・郵送・電話:合格者にのみ速達郵送や電話連絡で通知するケースもあります。郵送の場合、結果が翌日以降に判明することがあります。
複数校を受験する場合、合格発表が重なる日程では結果確認の段取りをあらかじめ決めておきましょう。
たとえば、発表時間が同時刻の場合、保護者が分担して各学校の結果をチェックするなどの対策が必要です。
また、合格後の入学手続き締切にも注意が必要です。私立小では合格発表から1~3日以内に入学金の納付など手続きを行わなければ合格が無効となるため、複数合格した場合の判断が早急に求められます。
万一第一志望に不合格でも、東京都内では公立小学校への就学通知が毎年10月頃に届くため、結果に一喜一憂せず次のステップに目を向けることが大切です。
「1日2校」受験は可能?併願スケジュールと注意点
「1日2校受験」とは、同じ日に午前と午後で異なる小学校の試験を受けることを指します。
結論としては、スケジュール次第で1日に2校受験することは可能です。
実際、東京の小学校受験では複数校を併願することが一般的で、試験日程が重ならないよう計画しているご家庭が多く見られます。
たとえば、11月1日の午前にA小学校、午後にB小学校を受験するケースもあります。
ただし、1日2校受験には以下の注意点があります。
試験日程の情報収集:
志望校の試験日が事前に公表される場合は、願書配布時や学校説明会でしっかり確認しましょう。
複数校の日時が重ならないかカレンダーに記入し、組み合わせを検討します。
人気校同士では同日の試験が組まれることがあるため、優先順位を決める必要があります。
移動手段と所要時間の計算:
午前の試験終了後、午後の試験集合時間までの移動時間を事前に計算し、余裕を持った移動計画を立てましょう。
東京都内は公共交通機関が発達していますが、ラッシュや渋滞に注意が必要です。
必要に応じてタクシーを利用するなど、余裕を持ったスケジュール調整が求められます。
持ち物・服装の準備:
午前と午後で受験校が異なっても、基本的な服装は統一して問題ありません。
ただし、午前の試験で子どもが汗をかいたり汚したりする可能性があるため、替えのシャツやハンカチなどの準備をしておくと安心です。
また、移動中の軽食も準備しておきましょう。
子どものコンディション管理:
1日に複数回の試験を受けるのは小さなお子さんにとって大きな負担となるため、前日は十分な睡眠を取り、当日はリラックスできるように工夫してください。
午前の試験がうまくいかなかった場合も、午後にリセットできるような声かけを行うと良いでしょう。
先輩ママの体験談によると、
「娘と11月1日に午前・午後で2校受験しました。移動はタクシーを使い、なんとか間に合わせましたが、親は終日疲れました。それでも、併願校に合格が決まったことで安心感が得られました」
とのことです。
併願スケジュールを立てる際は、「ここまで受けられれば上出来」という基準をあらかじめ決め、無理な受験を避けることが成功の鍵となります。
面接の入り方・入室の仕方完全解説【父親の役割も】
小学校受験の親子面接は、お子さんだけでなく保護者の振る舞いも評価される重要な場面です。
特に面接室への入室時のマナーは第一印象を左右します。
以下、面接室への正しい入り方(入室マナー)と、父親の役割についてステップ形式で解説します。
【面接室への入室ステップとマナー】
入室前のノックと返答:
面接室の前で親子で整列し、ドアをノック(3回程度)します。
中から「どうぞお入りください」という返事があれば、親子全員で「失礼いたします」と挨拶します。
ドアの開閉と入室の順序:
ドアは父親または先導する保護者が両手で静かに開けます。
入室の順番は、父親→子ども→母親の順が一般的です。
母親は最後に入室し、静かにドアを閉めます。
入室後の挨拶と着席:
入室後は面接官に向かって家族揃って「よろしくお願いいたします」と挨拶し、一礼します。
多くの場合、面接官から「おかけください」と促された後に着席します。
座るときの所作:
着席時は面接官に一礼してから「失礼いたします」と述べ、静かに座ります。
子どもが自分で座れるように促すのが理想です。
座った後は膝を揃え、背筋を伸ばして待機します。
面接中の姿勢と視線:
面接中は親子ともに良い姿勢を保ち、面接官の話を聞く際には適度にうなずくなど、しっかりと相手の目を見ながら話すことが重要です。
退室のマナー:
面接終了時は、親子全員で「本日はありがとうございました」とお礼を述べ、一礼して退室します。
退室の際も、父親が先にドアを開け、順番に退出するのが一般的です。
父親の役割としては、特に入室時に先頭を切ることが重要です。
父親が堂々と率先して行動することで、面接官に家庭全体のしっかりとした準備が伝わります。
面接官からは、家庭内で父親も積極的に教育に関与しているかどうかを評価される傾向がありますので、想定される質問に対して自らの言葉で答えられるよう、事前に夫婦でシミュレーションを行いましょう。
元小学校面接官は「入室の所作から退出まで一連の動作にはご家庭の雰囲気が表れる。父親が先頭でしっかりとリードし、親子で一体となって受け答えする姿勢が理想的」とコメントしています。
模試はいつ受けるべき?おすすめの時期と活用法
小学校受験の模試(模擬試験)は、受験本番前にお子さんの実力を測り、試験形式に慣れるための大切な機会です。
ここでは、模試を受けるタイミングとその活用法について説明します。
【模試を受けるおすすめの時期】
年中の秋~冬(試験約1年前):
年中から受験勉強を始めている場合、試験1年前の秋(11~12月)頃に模試を受けることで「場慣れ」と「弱点把握」を目的とします。
結果が低くても気にせず、現状の総合力を把握するためのテストと捉えます。
年長の4月~6月(試験約半年前):
年長になり本格的な受験対策が始まった時期です。
この時期に模試を受けることで、仕上がりの度合いを確認し、必要な改善点を洗い出します。
場合によっては志望校別の合格判定模試に挑戦するのも有効です。
年長の7月~9月(試験直前期):
夏休み前後の時期は、本番直前の最終ラウンドとして模試を受け、最終的な仕上げの確認を行います。
連続受験で疲弊しないよう、月2回程度に留めるのが望ましいです。
【模試結果の活用法】
弱点分野の洗い出し:
模試の設問ごとの正答率を分析し、苦手な分野を明確にします。
結果をもとに、家庭学習や塾の補習で重点強化を図りましょう。
学習計画の見直し:
模試の結果を踏まえ、今後の学習計画を再度立て直します。
得点が低かった部分は、重点的に復習を行い、得意分野は維持するなどメリハリのある計画にアップデートします。
本番シミュレーション:
模試は試験会場の雰囲気や制限時間の中で取り組む練習の機会でもあります。
実際の受験と同様に、服装や持ち物を整えて臨むことで、本番への準備になります。
志望校選定の参考:
模試で出る合格判定や偏差値は、志望校選びの参考材料になります。
ただし、模試結果はあくまで目安として捉え、最終判断は家庭で慎重に検討しましょう。
模試は単に受けるだけでなく、結果を次の対策に生かすことが重要です。
結果に一喜一憂せず、前向きに次への学習につなげる姿勢が合格への近道です。
東京の国立小学校ランキングと倍率一覧
東京都内には、国立大学附属小学校が複数あり、人気の高さから倍率も非常に高くなっています。
ここでは、国立・公立の小学校の競争倍率を概算値で紹介します。(倍率は2024年度入試時点の概算値です。)
東京学芸大学附属竹早小学校:
倍率は約66倍。抽選通過率25%、二次選考倍率7~8倍という厳しい選考が行われています。
お茶の水女子大学附属小学校:倍率は約58倍。女子は実質70倍近く、一次抽選通過率15~20%程度です。
筑波大学附属小学校:
倍率は約30倍。毎年約4,000人が志願し、学力検査を経て厳選されます。
東京都立立川国際中等教育学校附属小学校(都立):
倍率は約24倍。定員が男女各29名と少なく、英語教育に力を入れている学校です。
東京学芸大学附属大泉小学校:
倍率は8~9倍程度。通学圏が限定されており、応募条件が厳しくなっています。
東京学芸大学附属小金井小学校:
倍率は約7倍。定員は男女各20名程度で、通学条件が設定されています。
東京学芸大学附属世田谷小学校:
倍率は約5~6倍。地区限定の募集となっており、合格の可能性は他校と比べて高い傾向にあります。
なお、東京都内の私立小学校では倍率が一般的に3~10倍程度となっています。
国立と比較すると低い倍率に見えるかもしれませんが、どちらも厳しい選考が行われるため、併願受験でリスクヘッジすることが望ましいです。
写真撮影・服装・願書対策まで:家でできる準備まとめ
ここでは、家庭でできる受験準備として、願書用写真の撮影、受験時の服装、願書対策についてまとめます。
各項目をしっかり準備して、合格に向けた自信をつけましょう。
願書用写真の撮影ポイント
願書に貼付する写真は、お子さまの第一印象を決める大切な要素です。また、学校によっては家族写真の提出が求められる場合もあります。以下のポイントに注意して撮影しましょう。
撮影時期:
願書写真は、提出日から3ヶ月以内の撮影が求められることが多いため、願書提出の時期から逆算して夏~初秋(7~9月)に撮影するのが望ましいです。撮影予約は早めに行いましょう。
写真館の活用:
実績のある写真館での撮影がおすすめです。カメラマンが照明、背景、ポーズを指導してくれるため、仕上がりが綺麗に仕上がります。
写真館によっては服装レンタルや家族写真プランも用意されているので、口コミなどを参考に選んでください。(写真撮影スタジオ例はこちら)
服装と髪型:
撮影時の服装は試験当日と同じ格好が望ましいです。
子どもはフォーマルな受験用スーツ、親も面接時のスーツ姿で臨むようにしましょう。
家族写真の場合は全体の色味を統一するとよいです。髪型は、額や表情が隠れないように整えます。
表情と姿勢:
明るく爽やかな表情を心がけ、姿勢は胸を張って立つように練習しましょう。
写真館ではカメラマンが適宜指導してくれますので、リラックスして撮影に臨むと良いです。
撮影枚数と選別:
複数枚撮影してからベストショットを選び、応募する学校ごとに必要なサイズに合わせて準備します。写真は貼付前にしっかりと確認してください。
服装の準備(親子の身だしなみ)
受験当日の服装は、親子ともに面接官に与える印象を大きく左右します。以下は一般的な服装の準備ポイントです。
【子ども(男の子)】
白シャツ+紺色半ズボン+紺のジャケットまたはベスト、白い靴下、黒い革靴が基本です。受験スーツは事前に試着し、動きやすさやサイズを確認しましょう。
【子ども(女の子)】
白襟ブラウス、濃紺のジャンパースカートまたはワンピース、ボレロ、白ハイソックスまたは紺ソックス、ストラップシューズが定番です。
スカート丈や髪型にも注意し、上品な印象になるよう整えます。
【母親】
紺色無地のスーツ、またはワンピース+ジャケットで、膝丈のスカートまたはワンピースに落ち着いた色味のものを選びます。
ナチュラルメイク、結婚指輪やパールのイヤリング、シンプルなハンドバッグを合わせると良いでしょう。
【父親】
ダークスーツ(紺、濃グレー、黒)、白シャツ、シンプルなネクタイ、黒の革靴を着用します。
髪型は短髪清潔に整え、腕時計はシンプルなものが望ましいです。
服装の準備は、事前に全員で試着し、写真撮影も兼ねて確認すると安心です。
動きにくさやトラブルがないかチェックし、予備の持ち物(替えの服、ストッキング、予備のハンカチなど)も準備しておきましょう。
願書(志望理由書)の対策
願書は、ご家庭やお子さんの情報を学校に伝える大切な書類です。以下のポイントに注意して作成してください。
出願書類の種類を確認:
各校の募集要項に記載されている願書や家庭状況調書、作文などの提出書類を事前に確認し、期限までに全て準備しましょう。
志望理由の書き方:
学校ごとの教育方針や校風を理解し、「その学校だからこそ」という具体的な理由を記載します。
お子さんの長所や家庭の教育方針を盛り込み、熱意を伝える内容にしましょう。
家庭の教育方針・長所短所:
ご家庭で大切にしている教育理念や、お子さんの性格・特性について、具体的なエピソードを交えて記載します。
ネガティブな表現は避け、前向きな内容にまとめます。
下書きと添削:
まずは下書きを作成し、幼児教室の先生や受験経験者に添削してもらいましょう。
客観的な意見を取り入れて、文章の構成や表現を改善します。
清書と仕上げ:
清書用紙に黒のボールペンまたは万年筆で丁寧に書き、誤字脱字がないか十分にチェックします。
書類のコピーを保管し、面接時の参考にするのも有効です。
願書対策は早めに取り組むことが肝心です。志望理由を何度も推敲し、家族で内容を共有しておくと、面接での回答にも一貫性が生まれます。(願書の書き方に関しては、詳しくはこちらの記事へ)
家庭でできるその他の準備
受験に向けた家庭での取り組みは、以下のようなものがあります。
生活習慣・マナーの定着:
毎日の挨拶、正しい座り方、靴の整え方など、基本的な生活習慣を身に着けさせます。
これらは面接や行動観察の際に自然と表れ、良い印象を与えます。
巧緻性や運動の練習:
折り紙、紐結び、ハサミでの切り貼りなど、受験対策として必要な手先の器用さを、家庭内での遊びを通じて養います。
また、運動も体力維持や集中力向上に役立ちます。
知的好奇心を育む会話:
日々の会話で子どもに質問し、考えを話す練習をしましょう。
絵本や図鑑を活用し、語彙力と理解力を高めることも効果的です。
体調管理とメンタルケア:
栄養バランスの良い食事、十分な睡眠、そして適度な休息を取ることが大切です。
お子さんのストレスを軽減するために、家庭でリラックスできる時間を設けるよう心がけましょう。
以上、家庭での受験準備について、写真撮影、服装、願書対策を中心に解説しました。
東京の小学校受験は競争が激しいものの、準備が整っていれば自信を持って本番に臨むことができます。
ご夫婦で協力しながら、お子さんを支え、合格発表の日に笑顔で迎えられるようしっかりと対策を進めてください。
今後の受験対策や学校選びにお役立ていただければ幸いです。
関連記事を読むことで子供の教育のさらに深い知識を知ることができます。

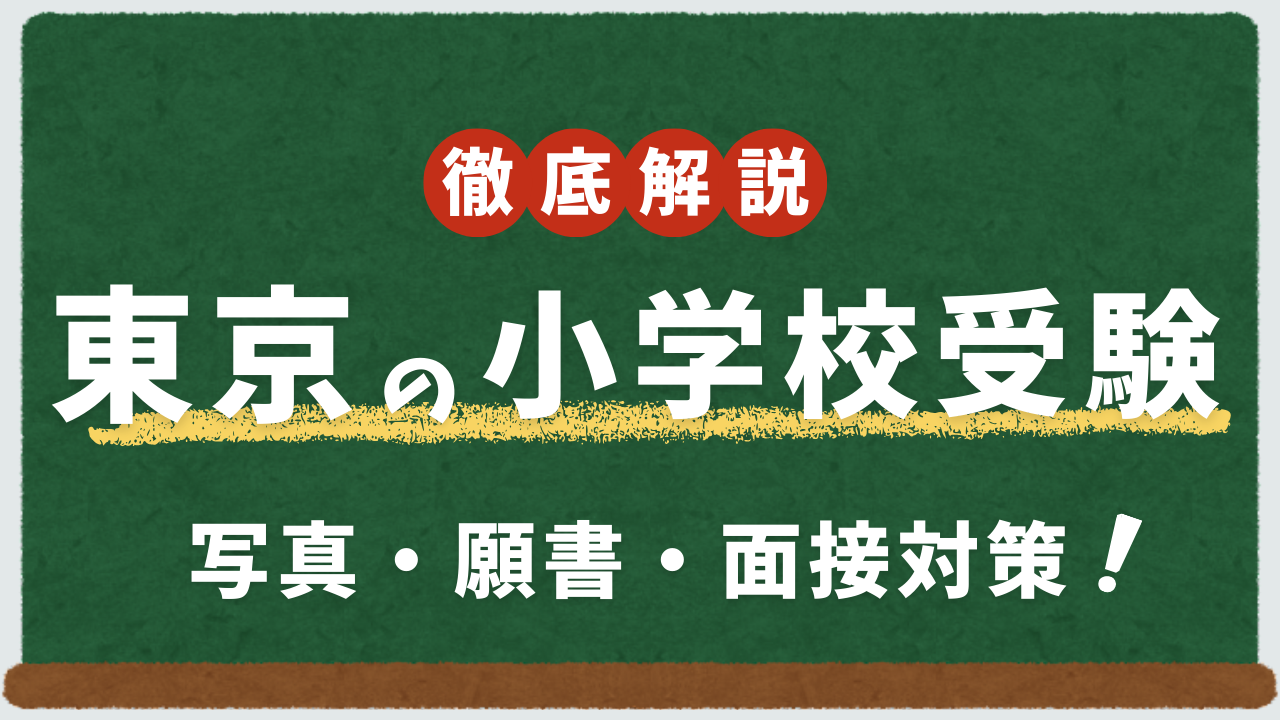
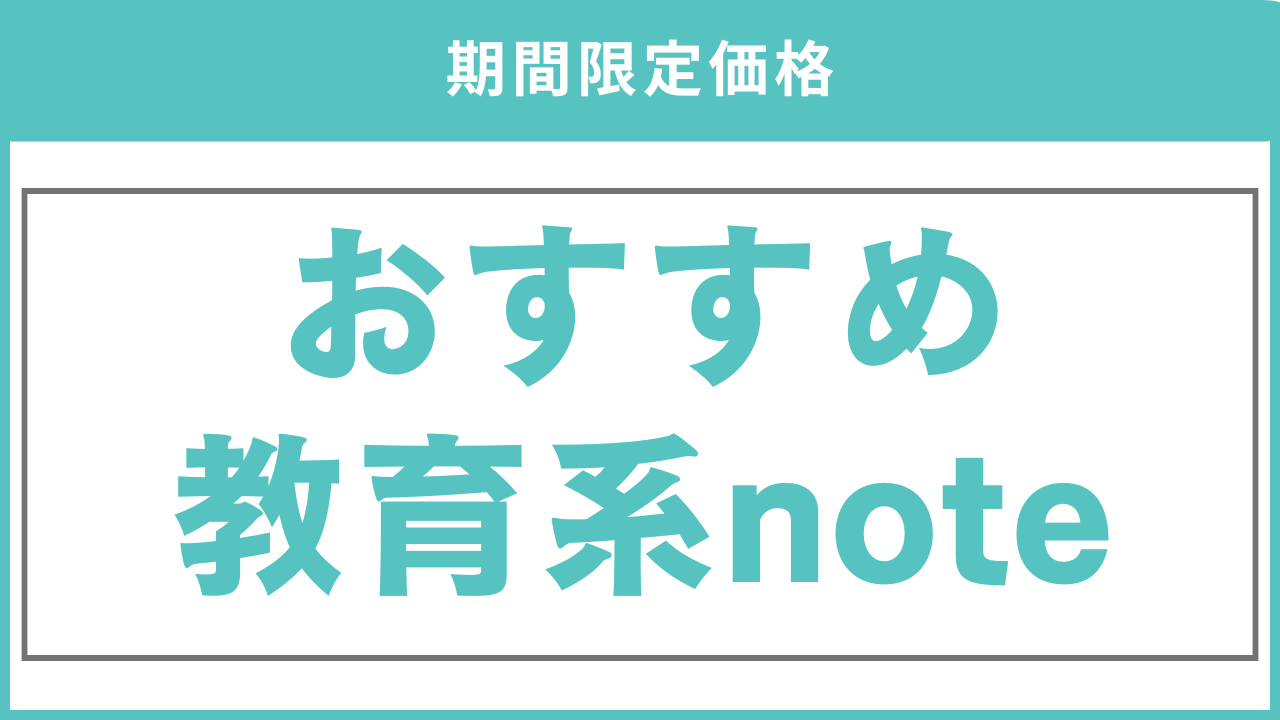


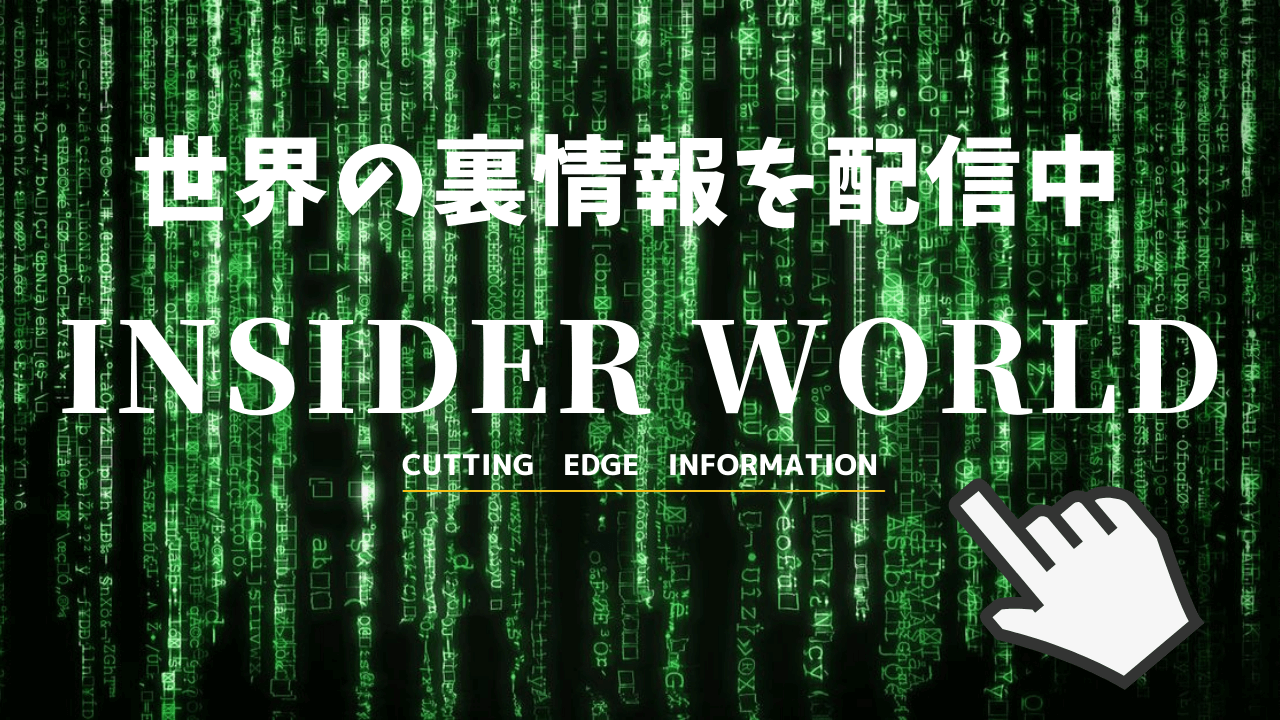


コメント