Masakiです。
ここ数年で、共働きで子育てをする家庭が珍しくなくなってきました。
夫婦のどちらも仕事を持ち、育児や家事を両立する生活は当たり前になりつつあります。
しかし、その一方で
「毎日時間が足りない」
「ご飯を作る余裕がない」
「保育園に入れなくて困っている」
「家事の負担が偏って不公平に感じる」
といった悩みを抱える家庭も多いのが現実です。
本記事では、共働き家庭を主な対象に、未就園児(保育園・幼稚園に入る前の子)から小学生まで幅広い子育てステージにおける課題と解決策を網羅的に解説します。
これから結婚や出産を考えている方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。
家事・育児・保育園の利用・家計管理・時間の使い方といったテーマごとに、共働き家庭のリアルな悩みにおける対処法やコツを紹介します。
共働き子育て家庭の現状とよくある悩み
共働きで子育てをする家庭は年々増加しています。
日本では夫婦のいる世帯の約7割が共働きとなっており(2020年時点)、今や専業主婦世帯よりも共働き世帯の方が主流です。
また、厚生労働省の調査によると子育て中の母親の約7割が仕事を持っており、育児と仕事を両立しているのが当たり前の時代になりつつあります。
共働きで得られるメリットも多く、例えば収入が増えて家計に余裕が出たり、互いに支え合うことでリスクに備えられるといった利点があります(片方が失職・病気になってももう一方の収入で支えられるなど)。
また、親がそれぞれ仕事を通じて社会に関わり充実感を得られることは、家庭にも良い影響をもたらします。
子どもにとっても、保育園や学童で友達と遊ぶ経験は社会性や適応力を育む機会になります。
一方で、共働きで子育てをする中では特有の悩みも生じがちです。
以下は、共働き子育て家庭によく見られる悩みの例です。
・家事や育児の負担が妻(母親)に偏り、「自分ばかり大変」と不公平感を抱きやすい
・子どもが病気になったときに仕事を休んだり早退したりする必要があり、職場調整や看病に苦労する
・保育園の送り迎えや行事対応などで残業ができず、独身時代のような働き方が難しい(キャリアを諦めている感覚)
・平日はとにかく時間がなく、自分の趣味や休息の時間がほとんど取れない
・毎日のご飯作りまで手が回らず、「ちゃんとした食事を作れない」ことにストレスを感じる
・朝早くから夜遅くまでフル回転で、睡眠不足が常態化しがち
・共働きゆえにママ友との交流が減り、育児の悩みを共有しにくい(孤独感を感じる)
・親子で過ごす時間が少なく、「子どもに寂しい思いをさせているのでは」と罪悪感に苛まれる
・希望する保育園に入れず、預け先の確保に頭を悩ませる(待機児童の問題)
こうした悩みは決して特殊なものではなく、多くの家庭が直面しています。
しかし、これらの悩みには先輩パパママたちの知恵や公的なサポート、ちょっとした工夫によって解決・緩和できるものも多くあります。
次の章から、テーマごとに具体的な解決策を見ていきましょう。
日々の生活にすぐ取り入れられるステップやコツも紹介しますので、ぜひできるところから実践してみてください。
子どもの成長段階ごとの主な課題
乳児〜未就園児期(0〜2歳)
24時間体制の育児が必要な時期です。
夜間の授乳や夜泣きで夫婦とも睡眠不足になりがちで、体力的・精神的に最も大変な時期ともいえます。
育児休業制度を夫婦で最大限活用し、お互いに交替で休息を取るようにしましょう。
産後うつや夫婦のすれ違いも起きやすいので、積極的に対話し、周囲のサポートも頼りながら乗り切ります。
実家の両親にしばらく手伝いに来てもらう、自治体の産後ヘルパー制度を利用するといった選択肢も検討しましょう。
幼児・就園児期(3〜5歳)
保育園や幼稚園に通い始める時期です。
子どもが集団生活に慣れるまで親も神経を使いますが、生活リズムを整える良い機会です。
行事や送り迎えで親の負担もありますが、延長保育や一時預かりを利用して仕事との両立を図ります。
イヤイヤ期やかんしゃくなど情緒面の成長も見られ、忙しい中でも子どもの気持ちに寄り添う対応が求められます。
朝晩のスキンシップや会話を大切にし、短い時間でも愛情を伝えるよう心がけましょう。
学童期(6〜12歳)
小学校入学により生活パターンが変化します。
放課後は学童保育や習い事で対応しますが、学校行事(授業参観や運動会など)が平日に行われることも多く、仕事との調整が必要です。
有給休暇を計画的に使い、可能な範囲で参加してあげましょう。
また、宿題のチェックや学校からのお便り対応など、親が見るべきこともあります。
子ども自身は低学年のうちはまだ手がかかりますが、高学年になると留守番や簡単な家事を任せることもできるようになります。
徐々に子どもの自立心を育みつつ、必要なサポートは続けましょう。
共働きで子育てをする上で大切なポイント
共働きで子育てを乗り切るためには、いくつか押さえておきたい大切なポイントがあります。
ここでは、家事や保育園といった個別のテーマに入る前に、共働き家庭全般に通じる基本的な心構えや工夫を確認しましょう。
夫婦がお互いを支えあい、子どもの健やかな成長を見守るために意識したいポイントを紹介します。
夫婦はチーム!コミュニケーションと協力が鍵
まず何よりも、夫婦で「チーム」として協力する意識を持つことが大切です。
家事・育児・仕事の両立は、一人で背負い込んでは到底こなせません。
お互いに状況を報告・相談し合い、協力して課題に対処していきましょう。
日々の情報共有を習慣に
子どもの園や学校での様子、体調や機嫌、翌日の予定などを夫婦で共有します。
忙しくても朝食や夕食の時間、就寝前のひとときに会話する時間を作り、お互いに必要な情報を伝え合いましょう。
LINEや共有カレンダーアプリを使って連絡事項やスケジュールを可視化するのも効果的です。
役割分担と柔軟な助け合い
基本的な家事・育児の役割分担は決めつつも、状況に応じて柔軟にカバーし合う姿勢が必要です。
「今日は残業で遅くなるから、ご飯の支度をお願い」
「明日は朝早いから子どもの支度は代わりにやるね」
など、その都度声をかけ合い、臨機応変に協力しましょう。
一方が大変なときはもう一方がサポートするという意識が、夫婦間の信頼感にもつながります。
相手への感謝と尊重を忘れない
忙しいとつい相手のミスや不足ばかりに目が行きがちですが、お互い頑張っていることを認め、感謝の言葉を伝えることも大切です。
「ゴミ出ししてくれて助かったよ」
「子どもをお風呂に入れてくれてありがとう」
など、小さなことでも声に出して伝えましょう。
そうしたポジティブなコミュニケーションが、チームとしての一体感を高め、困難な状況も乗り越えやすくします。
周囲のサポートは遠慮なく活用する
共働き育児は夫婦二人だけで完璧にこなそうとせず、利用できる支援は積極的に活用することが成功の鍵です。
身近な家族や行政・民間のサービスなど、頼れるものには遠慮なく頼りましょう。
親族や友人に協力をお願い
もし実家の両親が近くに住んでいるなら、時折子どもの世話をお願いしてみましょう。
週末の数時間だけでも預かってもらえれば、その間に夫婦で買い物や用事を済ませたりリフレッシュしたりできます。
また、信頼できる友人同士で「お互いの子どもを交互に預かる」ような助け合いをしている例もあります。
周囲に頼れる人がいれば、適度に力を借りることは決して悪いことではありません。
地域の子育て支援を利用
自治体やNPOが提供する子育て支援サービスも有効です。
例えば、ファミリーサポートセンターでは地域のボランティアが保育園の送迎や一時預かりを有償で引き受けてくれる場合があります。
また、ベビーシッターサービスや民間の一時保育所なども選択肢です。
費用はかかりますが、仕事がどうしても休めないときなど「いざ」という場面で登録しておくと安心です。
職場の制度を確認
勤務先に子育て中の社員向けの制度がないか確認しましょう。
育児短時間勤務制度や在宅勤務制度、看護休暇(子どもの病気の際に取得できる休暇)などが整っていれば積極的に活用します。
また、会社によってはベビーシッター利用補助や社員向けの保育施設提携があるケースもあります。
上司や人事に相談し、利用できる制度は遠慮なく使いましょう。
共働きで頑張る社員を支援する制度は年々整いつつあります。
また、これから出産を控えている場合は、ぜひ夫婦で育児休業の取得についても検討してみてください。
近年は男性の育休取得も推進されており、交代で休業を取ることで子育て初期の負担を大きく減らすことができます。
「完璧主義」を手放し肩の力を抜く
真面目なパパママほど
「家も仕事も育児も全てきっちりやらなければ」
と完璧を目指してしまいがちです。
しかし、共働きで時間が限られる中では、何もかもを完璧にこなすのは不可能です。
時には手を抜いたり周囲に甘えたりすることも必要になります。
優先順位をつける
限られた時間とエネルギーの中で何が一番大事か考えましょう。
子どもの安全と健康、夫婦や家族の心身の健康がまず最優先です。
部屋が多少散らかっていても命に関わりませんし、毎日手料理でなく外食の日があっても構いません。
「ここだけはやるが、ここは多少妥協する」というラインを決めると心が楽になります。
手抜きは恥じゃない
ときには家事を簡略化したりすることを自分に許可しましょう。
例えば夕食は冷凍保存しておいたものを活用するなど。
「毎日ちゃんとやらなきゃ」と思い詰めず、疲れているときは楽をしたってOKです。
自分自身のケアも忘れずに
完璧を求めて頑張りすぎると、パパママ自身が倒れてしまっては元も子もありません。
ときには意識して休息を取りましょう。
短時間でも趣味を楽しんだり、お風呂にゆっくり浸かったりする時間を確保してリフレッシュすることも大切です。
心に余裕が生まれると、子どもにも穏やかに接することができます。
子どもとの時間を質良く、愛情を伝える
共働きでどうしても子どもと過ごす時間が少なくなる分、「質」を高める工夫をしましょう。
また、限られた時間でもしっかり愛情を伝えることで、子どもは安心感を得られます。
1日15分でも濃密なふれあいを
忙しい日々でも、子どもと向き合う時間を意識的に作ります。
例えば寝る前の読み聞かせやハグをする時間、保育園から帰った後にその日の出来事を聞いてあげる時間など、短時間でも子どもが「パパ・ママは自分の話を聞いてくれる」「愛されている」と感じられるコミュニケーションを心がけましょう。
週末は家族の思い出づくりを
休日はできるだけ家族で過ごす時間を確保します。
公園に行って遊ぶ、一緒に料理をする、家族の思い出に残るような体験を積極的に作りましょう。
難しく考えずとも、子どもにとっては親と一緒なら何気ない遊びも特別な時間になります。
罪悪感より前向きな姿勢を
働いていることで子どもに寂しい思いをさせているのでは…と罪悪感を抱く親御さんも多いですが、その気持ちを必要以上に引きずれこまないようにしましょう。
子どもは順応性が高く、保育園や学校生活で友達と過ごすのも楽しい時間です。
大切なのは、限られた時間でも子どもを思いやる気持ちを伝えることです。
「いつも応援しているよ」
「大好きだよ」
といった言葉かけやスキンシップを欠かさず、愛情が十分に伝われば、子どもは安心して成長してくれます。
親が生き生きと働く姿を見せることも、将来子どもが社会に出るときの良いモデルになりますので、自信を持って仕事にも取り組みましょう。
一人っ子育児ならではの工夫も
本記事では子ども1人の家庭を前提としていますが、一人っ子の子育てには特有の工夫もあります。
兄弟姉妹がいない分、子ども同士で遊ぶ機会が少なくなりがちなので、意識的に他の子どもと触れ合う場を作ってあげると良いでしょう。
積極的に交流の場を
保育園や学校での友達付き合いのほか、地域の子育てイベントや習い事などで同年代の子と交流できる機会を増やしてあげます。
そうすることで、子どもが孤独を感じにくくなり、コミュニケーション能力も育まれます。
自分で遊ぶ力を伸ばす
一人遊びが上手な子は、親が忙しいときでも退屈せず過ごせます。
絵本や積み木、お絵描きなど、一人でも集中できる遊びの環境を整えてあげましょう。
ただし、長時間のタブレットやゲームに頼りきりになるのは避け、バランスを考えます。
ちょっとしたお手伝いを任せる
一人っ子だと親の関心が集中しやすい分、甘えん坊になったり依存的になるのではと心配する声もあります。
そうならないためにも、小さい頃から簡単な家のお手伝いを任せてみましょう。
おもちゃの片付けやテーブル拭きなど子どもにできることをお願いすると、子どもは張り切ってやってくれるものです。
自立心が育つうえ、親も助かり一石二鳥です。
これらのポイントを踏まえることで、共働きであっても家族の絆をしっかり保ち、子どもの健やかな成長を支えることができます。
次章からは、具体的な場面(家事、保育園、家計、時間管理)ごとの課題と対策を詳しく見ていきましょう。
家事も育児も私ばかり? 不公平感をなくすには
共働き家庭では「結局、自分(主に妻)ばかりが家事育児を担っている」と不満が募り、夫婦仲がぎくしゃくするケースも少なくありません。
実際、日本の調査でも共働き家庭における夫の家事・育児分担割合は2割程度とされており、まだまだ妻側の負担が大きいのが現状です。
妻が家事育児をほぼ一人で回す、いわゆる「ワンオペ育児」の状態になってしまうと心身の疲労も限界に達しかねません。
ここでは、家事負担の不公平感を解消し、夫婦が納得して協力できる家事分担の進め方や工夫を紹介します。
家事分担を話し合いで明確にする
まずは、夫婦で現状の家事・育児の役割分担について率直に話し合ってみましょう。
お互いどのくらい家事をしているか意識がズレている場合も多いため、言葉に出して共有することが重要です。
「あなたはこれだけやってくれて助かっている」
「ここは負担が偏っているので見直したい」
といった形で、責めるのではなく建設的に改善策を議論します。
話し合いのポイントは、感情的にならず冷静に、そして具体的に進めることです。
「もっと協力してよ」
ではなく、
「平日の洗濯物たたみを手伝ってもらえると助かる」
「子どものお迎えはできれば交代制にしたい」
など、具体的なタスクやタイミングを挙げて提案します。
また、夫婦それぞれの得意・不得意や勤務時間帯も考慮に入れましょう。
料理が得意な方が食事担当、朝強い方が朝の子どもの支度担当、といったように分担するとスムーズです。
家事分担表を作るステップ
口頭で決めただけだと、時間が経つうちにうやむやになったり認識がずれてくる恐れがあります。
そこで、合意した分担内容は紙やホワイトボードに「見える化」しておくのがおすすめです。
以下のステップで家事分担表を作成してみましょう。
1. 家事・育児タスクを書き出す
まずは日常の家事(掃除、洗濯、炊事、皿洗い、ゴミ出し、買い物など)と育児(送り迎え、食事補助、入浴補助、寝かしつけ、学校行事対応など)のすべてのタスクを洗い出します。
細かい項目まで漏らさずリストアップすることが重要です。
2. 担当者と頻度を決める
リストアップした各タスクについて、どちらが主に担当するか、あるいは状況に応じて交代で行うのかを決めます。
同時に、週何回・どのタイミングで行うか(毎日なのか、週末まとめてなのか等)もすり合わせましょう。
双方の勤務時間帯や得意分野を踏まえて、「朝は夫が子どもの世話、夜は妻が子どもをお風呂に入れる」「料理は妻、後片付けは夫」など具体的に役割を割り振っていきます。
3. 分担表に書き出す
決まった内容を表にまとめます。
曜日ごと、時間帯ごとに「誰が何をするか」を書き込み、視覚的に一覧できるようにします。
手書きで紙に書いて冷蔵庫に貼る方法でも良いですし、家事分担アプリを利用して共有するのも便利です。
4. 実践し調整する
実際にその分担で生活を回してみて、うまくいかない点があれば適宜見直します。
無理が生じている場合は役割を交換したり、タスク自体を減らすことも検討しましょう。
一度決めたら終わりではなく、家庭の状況変化(子どもの成長や仕事量の変化など)に応じて柔軟にアップデートすることが大切です。
5. 定期的に振り返る
月に一度でもよいので、家事分担の状況を夫婦で振り返り、「不満が溜まっていないか」「改善できることはないか」を話し合います。
小さなわだかまりを放置せず解消していくことで、大きな不満や喧嘩に発展するのを防げます。
以上のように家事分担表を作っておけば、お互いの責任範囲が明確になるため、「何をやるべきか」の認識違いや「自分ばかりやっている」という不満が起きにくくなります。
実際に、ある共働き家庭の妻は「夫に遠慮して自分ばかり頑張っていましたが、限界が来て思い切って頼ったところ、夫も負担に気づいて動いてくれるようになりました」と振り返っています。
お互いに状況を共有すれば、家事分担が改善したという例も多いのです。
ぜひ一度試してみてください。
家事を時短・省力化する工夫
家事そのものの負担を減らす工夫も並行して取り入れましょう。
全てを手作業で完璧に行おうとすると、どうしても時間も手間もかかってしまいます。
現代には共働き家庭の強い味方となる便利な家電やサービスが豊富にありますので、積極的に活用して夫婦の負担を減らします。
食器洗い乾燥機
食後の皿洗いに費やす時間を大幅に短縮できます。
ボタン一つで洗浄から乾燥まで任せられるので、夜の時間にゆとりが生まれます。
ロボット掃除機
床の掃除はロボットにお任せ。
留守中に自動で家中を掃除してくれるため、帰宅後に床掃除をする手間が省けます。
洗濯乾燥機
洗濯から乾燥まで連続で行えるドラム式洗濯乾燥機なら、干す作業が不要になります。
夜間や外出中に回しておけば、洗濯物を干す・取り込む時間を節約できます。
ミールキット・宅配食材サービス
献立を考えて買い物に行き、一から料理を作る負担を減らせます。
ミールキットなら必要な食材とレシピがセットで届き、短時間で栄養バランスの良い食事を用意できます。
ネットスーパーや生協の宅配を利用すれば、重い食材や日用品の買い出しに行く回数も減らせるでしょう。
冷凍食品・惣菜の活用
市販の冷凍食品やスーパーのお惣菜も上手に取り入れて、調理にかかる時間と労力を減らしましょう。
特に忙しい平日の夕食は、メインだけ調理して副菜は惣菜に頼るなど、力の抜きどころを作ることがポイントです。
家事代行サービス
どうしても手が回らない家事がある場合、プロの手を借りるのも一つの手です。
月に1回でも掃除代行を頼めば、大掃除に近いレベルで家中を綺麗にしてもらえます。
費用は発生しますが、時間をお金で買うと割り切って検討してみましょう。
こうした時短家電やサービスへの初期投資・出費はありますが、長い目で見れば家族の時間や心の余裕を増やすことにつながります。
また、便利な道具を取り入れること自体が夫婦の家事シェアを促進することもあります。
例えば食洗機があれば「食器をセットしてスイッチを押す」だけなので、普段料理をしないパパでも後片付けを担当しやすくなる、といった具合です。
家庭の状況に合わせて無理なく利用できるものから取り入れてみてください。
保育園に入れない!? 共働き家庭の保活対策
共働き家庭にとって、子どもを保育園に預けられるかどうかは死活問題です。
しかし都市部を中心に待機児童(希望しても保育園に入れない子ども)の問題は依然として存在し、「保活」(保育園入園のための活動)が親にとって大きな負担となっています。
「申し込んだけれど落ちてしまった…」というケースでも、あきらめずに次の手を考えることが大切です。
この章では、保育園・学童の基本知識と、入園できない場合の対策について解説します。
希望の保育園に入るためのポイント
まず、保育園には大きく分けて認可保育園(国や自治体が認可した施設)と認可外保育施設(企業主導型保育や無認可保育所など)があります。
認可保育園は保育料が収入に応じて安く、公的補助も手厚い一方、人気地域では定員が足りず抽選や選考で入園が決まります。
なお、幼稚園と保育園の機能を併せ持つ認定こども園が増えており、3〜5歳児は幼稚園的な活動をしながら長時間の保育を受けられる場合もあります。
認可外施設は料金が高めですが比較的入りやすく、独自の特色(夜間保育、英語教育など)を持つ園もあります。
希望の保育園に入るためには、以下のポイントを押さえましょう。
早めに情報収集
自治体の保育課で入園募集要項を入手し、締め切りや必要書類を把握します。
また、地域の先輩パパママやインターネット上の育児コミュニティで保活の体験談を集めるのも有益です。
現実的な難易度やコツを知り、戦略を立てましょう。
年度途中入園よりも4月入園(新年度開始)の方が枠が多く入りやすいので、可能なら4月入園を狙いましょう。
また、希望する園の見学会に参加して雰囲気や方針を確認しておくと安心です。
第一希望にこだわりすぎない
人気園だけに絞らず、第2第3希望まで現実的に預けられる範囲の園をリストアップします。
自宅から遠すぎないか、延長保育の有無、園の方針などをチェックし、候補を複数準備しましょう。
選択肢を増やすことで入園できる確率も上がります。
ポイント(選考基準)を理解
認可保育園では両親の就労状況や勤務時間、祖父母の支援可否などを点数化して選考する自治体が多いです。
自分たちの世帯がどの程度のポイントになるのか、市役所で相談してみましょう。
もし夫婦の働き方調整でポイントが上がる場合(例:共にフルタイム就労など)は検討します。
ただし無理な働き方変更は本末転倒なので、可能な範囲で。
認可外も視野に入れる
どうしても認可園が厳しそうな場合、認可外の保育施設も選択肢に加えておきます。
費用負担は増えますが、背に腹は代えられません。
一時的に認可外に預け、翌年再度認可園を狙う家庭もあります。
企業主導型保育園は、勤務先によらず利用できる園も多く、比較的保育料も抑えめなので要チェックです。
保育園に入れなかった場合の選択肢
申請したすべての保育園に入れなかった場合でも、いくつか取れる手段があります。
絶望せず、次のような対策を検討してみましょう。
育児休業の延長
もし子どもが1歳になるタイミングで保育園に入れなかった場合、会社の制度で育休延長(最大2歳まで)を申請できることがあります。
職場に確認し、延長が可能ならば子どもが入園できるまで育休を延ばすのも一つの方法です。
一時的に在宅勤務や時短勤務に切り替え
勤務先が柔軟であれば、一時的にフルタイムから在宅勤務や時短勤務に変更させてもらえないか交渉してみます。
子どもの世話をしながら仕事をするのは大変ですが、家で見ながら働ければ保育園が見つかるまでの繋ぎにはなるかもしれません。
親族によるサポート
近くに頼れる親族(祖父母など)がいれば、一定期間子どもの保育をお願いできないか話してみましょう。
平日昼間だけでも来てもらえれば、その間に夫婦が交替で仕事に出ることができます。
ただし祖父母にも負担になるため、無理のない範囲でお願いすることが大事です。
認可外保育施設の活用
先述のように、無認可の保育所やベビーシッターに預ける選択もあります。
月額費用は高額になりますが、背に腹は代えられません。
自治体によっては認可外を利用した場合に一部補助金が出る制度もありますので調べてみましょう。
幼稚園+延長保育への切り替え
子どもが3歳以上の場合、思い切って幼稚園に入園させ、幼稚園の終了後に延長保育(預かり保育)を利用する手段もあります。
幼稚園は基本的に教育の場ですが、最近は共働き家庭向けに夕方まで預かってくれる園も増えています。
幼稚園なら途中入園できる枠があることもあるため、地域の幼稚園情報も確認してみましょう。
病児保育の登録
共働き家庭では、せっかく保育園に通い始めても子どもが病気で頻繁に呼び出されることがあります。
いざという時に備え、自治体の病児保育室や病児保育サービスに事前登録しておきましょう。
子どもが発熱して保育園に預けられない日でも、一時的に預かってもらえる施設があると心強いです。
小学校入学後の学童利用
子どもが小学校に入学すると、放課後の過ごし方が新たな課題となります。
共働きの場合、公設の学童保育(放課後児童クラブ)を利用する家庭が多いでしょう。
学童保育は通常、小学校低学年(1〜3年生程度)を対象に放課後から夕方まで子どもを預かってくれる施設です。
自治体に申し込みが必要で、こちらも希望者が多い地域では抽選や選考があります。
スムーズに学童を利用するために、以下の点に注意します。
学校からの案内をチェック
小学校入学前に、学校や自治体から学童保育の案内が配布されます。
申請時期を逃さないようにし、必要書類を期日までに提出しましょう。
共働き家庭であれば優先度は高いですが、定員超過の場合もあるので第2学童候補なども視野に入れておきます。
民間学童や習い事で補完
公立学童に入れない場合や、高学年になって公立学童の対象外になった場合は、民間の学童サービス(学童塾やスポーツクラブなど)を検討します。
有料ですが、宿題サポートや送迎付きのところもあります。
また、習い事を複数組み合わせて放課後の居場所を確保する家庭もあります。
ただし、移動が多くなると子どもも疲れるため、無理のない範囲で計画しましょう。
子どもの留守番訓練
高学年にもなれば短時間の留守番ができる子もいます。
徐々に家で一人で過ごす練習をさせるのも一案です。
その際はルールを決め、防犯対策(GPS付き携帯電話を持たせる、室内に見守りカメラを設置するなど)を講じて安全を確保します。
もちろん子どもの性格によるので、無理強いは禁物です。
不安が強い場合は無理に留守番させず、他の預け先を検討しましょう。
このように、子どもの成長段階ごとに預け先の選択肢や対策は変わってきます。
自治体や学校からの情報を常にチェックし、早め早めに準備を進めることが大切です。
共働きでも子どもが安心して過ごせる環境を整えられるよう、柔軟に対応していきましょう。
共働き家庭の家計管理と賢いお金の使い方
共働き家庭では収入が増える分、支出も増えがちです。
忙しさから家計管理が疎かになり、「知らぬ間にあまり貯金できていない」という事態にもなりかねません。
ここでは、無理なく貯蓄を増やし、上手にお金をやりくりするコツを紹介します。
将来の教育費やマイホーム資金なども見据え、計画的に家計を回していきましょう。
家計管理の基本:収支の見える化と貯蓄習慣
まず、家庭の収入と支出をきちんと「見える化」することが家計管理の出発点です。
共働きの場合、給与振込口座が別々になりやすく、それぞれが自由に使えるお金が多いため、気づいたら二人合わせてかなり使っていた…ということも起こり得ます。
以下の基本的な管理術を取り入れてみましょう。
夫婦で家計を共有する
毎月の収入合計と主な支出項目(住宅費、食費、光熱費、保育料、保険料、娯楽費など)を夫婦で一度洗い出し、家計全体の状況を把握します。
そのうえで、どちらがどの支出を負担するか、あるいは共通口座を作ってそこに生活費を入れるかなど、管理方法を決めましょう。
お互いの収入や支出を全く把握していない状態は避け、オープンに話し合うことが大切です。
貯金は先取りする
貯蓄を増やすには「余ったら貯める」ではなく「初めに貯める」が鉄則です。
給料日にはまず一定額を貯蓄用口座に移す、財形貯蓄や積立定期預金を利用して強制的に貯金する、といった仕組みを作りましょう。
共働きのうちに毎月まとまった額を先取り貯蓄すれば、将来の出費(教育費や住宅購入資金)に備える土台ができます。
支出を記録・把握する
忙しい共働きでも、家計簿アプリなどを使えば手軽に支出管理が可能です。
クレジットカードや電子マネーと連携できるアプリを導入し、何にいくら使っているか自動で可視化しましょう。
毎月の支出内訳が分かれば、節約できる無駄遣いや固定費の見直しポイントも見えてきます。
たとえば、夫婦それぞれが契約している動画配信サービスを一本化する、使っていないサブスクを解約するなど、固定費の見直しポイントも見えてきます。
一般に通信費や保険料などの固定費を見直すと、無理せず毎月の支出を減らせます。
忙しい共働きだからこそ、一度腰を据えて自動で出ていくお金をチェックしてみましょう。
定期的に家計会議を
数ヶ月に一度は夫婦で「家計会議」を開き、貯蓄額の進捗や大型出費の予定(旅行、家電購入、車検など)を確認しましょう。
二人で目標を共有し、「今年は○万円貯めよう」「○年後にマイホームを検討しよう」など将来の計画についても話し合います。
共通の目標があれば節約へのモチベーションも上がりますし、お金に関する価値観のズレも調整しやすくなります。
共働き家庭がお得に暮らすためのヒント
家計管理の基本ができたら、共働き家庭ならではのメリットを活かしてさらにお得に生活する工夫も試してみましょう。
各種手当・制度を確認
自治体から支給される児童手当は子どものために確実に貯蓄しておきます(使わずに別口座に積み立てる家庭も多いです)。
お子さんの教育費は中学以降徐々に増加し、高校・大学進学時にはまとまった費用が必要となるため、小さいうちから計画的に備えておきましょう。
また、医療費助成や高校授業料無償化など、子育て世帯向けの公的支援制度は漏れなく享受しましょう。
共働きで収入が高いと所得制限にかかる場合もありますが、自分達が該当する制度はないか定期的にチェックすることが大切です。
ポイントや福利厚生を活かす
日々の買い物はできるだけポイント還元率の高いクレジットカードや電子決済を利用し、家族の出費で効率よくポイントを貯めましょう。
貯まったポイントで日用品を購入すれば実質的な節約になります。
また、共働きならではの会社の福利厚生(提携施設の割引、社内預金制度、社員持株会など)もチェックし、利用価値があれば積極的に使います。
二人分の制度を駆使すれば、単身では得られないメリットも享受できます。
以上のような工夫を積み重ねることで、共働きの強みを活かしつつ堅実に家計を回していくことができます。
収入が多い分つい支出も増えてしまいがちですが、「将来のためのお金をしっかり確保する」という意識を夫婦で共有し、お金の不安を減らしていきましょう。
共働き家庭の時間管理術: 時間を生み出す工夫
共働きで子育てをしていると、「一日があっという間に終わってしまい、自分たちの時間が全然ない!」と感じることも多いでしょう。
仕事に育児に家事にと、24時間がいくらあっても足りないように思えるかもしれません。
しかし、時間の使い方を工夫することで、限られた中からでも自分たちの時間を捻出することは可能です。
ここでは、忙しい毎日の中で少しでも余裕を生み出すための具体的なステップとテクニックを紹介します。
忙しい共働き夫婦が時間を生み出す5つのステップ
1. 現状の時間の使い方を記録・分析する
まず、自分たちの一日の時間の使い方を見直すことから始めます。
平日5日間、起床から就寝までの行動を細かく書き出してみましょう。
通勤に何分、家事に何分、子どもの世話に何分かかっているか視覚化すると、「意外とスマホを見ている時間が長い」「この作業は毎日やらなくてもいいかも」など改善のヒントが見えてきます。
2. やめること・短縮できることを決める
記録を基に、「本当に必要なこと」と「やめても支障がないこと」を仕分けします。
たとえば毎日アイロンがけをするのをやめて週末まとめてにする、平日の掃除は最低限にとどめる、SNSを見る時間を減らす、といった具合に削れる時間を削ります。
また、仕事面でも残業を極力しないよう業務効率を上げる、引き受けすぎた用事は断る勇気を持つなど、時間確保のための優先順位付けを行いましょう。
3. 生活動線とルーティンを工夫する
日々の家事・育児の動線を工夫して無駄な時間を減らします。
例えば、朝起きてから出勤までの一連の流れを決めておき(朝食準備→子ども起こす→自分たちの支度→出発のように順序固定)、習慣化してしまいます。
前夜のうちに翌日の保育園の持ち物や自分たちの服を準備しておく、朝食はパンと前日の残りおかずで済ませるなど、朝のバタバタを減らす工夫をしましょう。
逆に夜は、子どもの寝かしつけ後に翌日の準備や簡単な家事を済ませ、就寝時間を確保します。
家事の時短アイデアについては前章で紹介した便利家電やサービスも活用し、「ながら家事」も取り入れて効率アップを図ります(例:料理しながら台所の片付けを並行して行うなど)。
また、通勤中にスマホでネットスーパーの注文を済ませておくなど、移動や待ち時間を有効活用することで、帰宅後の作業を減らすこともできます。
4. 夫婦でスケジュールを共有・調整する
夫婦がお互いの予定や日々の役割分担を把握しておくことも時間管理の鍵です。
Googleカレンダー等でお互いの勤務予定や子どもの行事予定を共有し、誰がいつ忙しいか見えるようにします。
そして、例えば「朝は夫が子どもの送り担当、夕方は妻がお迎え担当」のように時間帯で役割を分担したり、片方が忙しい週はもう一方が家事育児をカバーするなど、柔軟にスケジュールを調整しましょう。
あらかじめ夫婦間で合意しておけば、「急な残業で迎えに行けない!」というときも迅速に対応できます。
5. 自分たちの時間も予定に組み込む
最後に、あえて「何もしない時間」「リラックスする時間」をスケジュールに入れてしまうのも重要です。
忙しいとつい自分のことを後回しにしがちですが、計画に余白を持たせることで心身の疲れを癒やす時間が確保できます。
例えば「毎日夜10時以降は夫婦でゆっくり会話する時間にする」「金曜の夜は家事を休んで映画を見る」といったように、自分たちがホッとできる時間をルーティンとして組み込みましょう。
適度に休息を取ることで翌日の効率も上がり、結果的に時間の有効活用につながります。
小さな習慣の積み重ねが、思った以上に効果を発揮するものです。
以上のステップを実践することで、少しずつでも自分たちの自由に使える時間を生み出していくことができます。
完璧にこなすのは難しいですが、常に「もっと良いやり方はないか?」と意識するだけでも日々の時間の使い方は変わってくるはずです。
共働きだからこそ時間は貴重な財産です。
上手にやりくりして、仕事も家庭も充実させていきましょう。
共働き家庭のある1日(タイムスケジュール例)
6:00 夫・妻起床。それぞれ準備開始。妻は朝食(前夜に下ごしらえ済み)と夫のお弁当作り、夫は洗濯物を乾燥機にかけ、ゴミ出しなど朝の家事を担当。
6:45 子ども起床。一家で朝食をとる。妻は食べながら子どもの連絡帳に目を通し、検温など登園準備。
7:30 夫が子どもを保育園に連れて出発。妻は急いで食器を片付け(洗い物は帰宅後の食洗機に任せるため軽くすすぐだけ)、7:45に自宅を出て出勤。
8:30 夫・妻ともに仕事開始(この日は夫は定時退社、妻は時短勤務で16時退社予定)。
16:00 妻が職場を出発。途中でスーパーに寄らず、スマホのネットスーパーで注文しておいた食材が18時に届くようセット。
17:00 妻、保育園に子どもをお迎え。そのまま帰宅。
17:30 妻と子どもで帰宅。届いた食材を受け取りながら、妻はすぐ夕食作り開始。メニューは朝仕込んでおいた煮込みハンバーグ(温めるだけ)と、カット野菜のサラダ。
18:30 夫が仕事から帰宅。夫が子どもをお風呂に入れている間に、妻は夕食の仕上げと翌日の保育園準備(連絡帳記入など)。
19:00 一家で夕食。
20:00 夫が食器を食洗機にセットし台所を片付け。妻は子どもを寝かしつけ(絵本読み聞かせ)担当。
21:00 子ども就寝。夫は洗濯物を畳んで明日の各自の服を用意。妻は明日の夕食用に野菜を切って下ごしらえ。終わったら二人でリラックスタイム。
22:30 夫婦就寝(お疲れさまでした!)。
おわりに:共働き育児を無理なく続けるために
共働きで子育てをしていると、毎日が挑戦の連続です。
時間的な余裕のなさや予期せぬハプニングに途方に暮れることもあるでしょう。
しかし、本記事で見てきたように、工夫次第でその負担を軽減し、家族みんなが笑顔で過ごせる余地を作ることができます。
大切なのは、「完璧を目指しすぎないこと」と「一人で抱え込まないこと」です。
夫婦でしっかりコミュニケーションをとり、チームとして助け合いましょう。
そして、利用できる制度や周囲の助けは上手に借りてください。
家事代行や保育サービスを活用することも、決して怠けではなく賢い選択です。
何より、パパもママも自分を責めすぎず、適度に肩の力を抜いてください。
共働き子育てのやり方に「絶対的な正解」はありません。
各ご家庭で事情も価値観も異なりますから、「自分たちに合ったやり方」を模索していけば良いのです。
本記事で紹介した提案も、できるものから少しずつ試してみて、自分たち流にアレンジしてみてください。
なお、悩みを抱え込まず、自治体の子育て相談窓口や先輩ママ・パパに相談するのも良いでしょう。
同じ境遇の仲間と情報交換すれば励まし合いながらヒントを得られるかもしれません。
苦労も多いですが、その分得られるものもあります。
どうか頑張りすぎず、周りと支え合いながら、共働き育児を無理なく続けていってくださいね。
あなたの家庭にとってベストなバランスが見つかりますように。
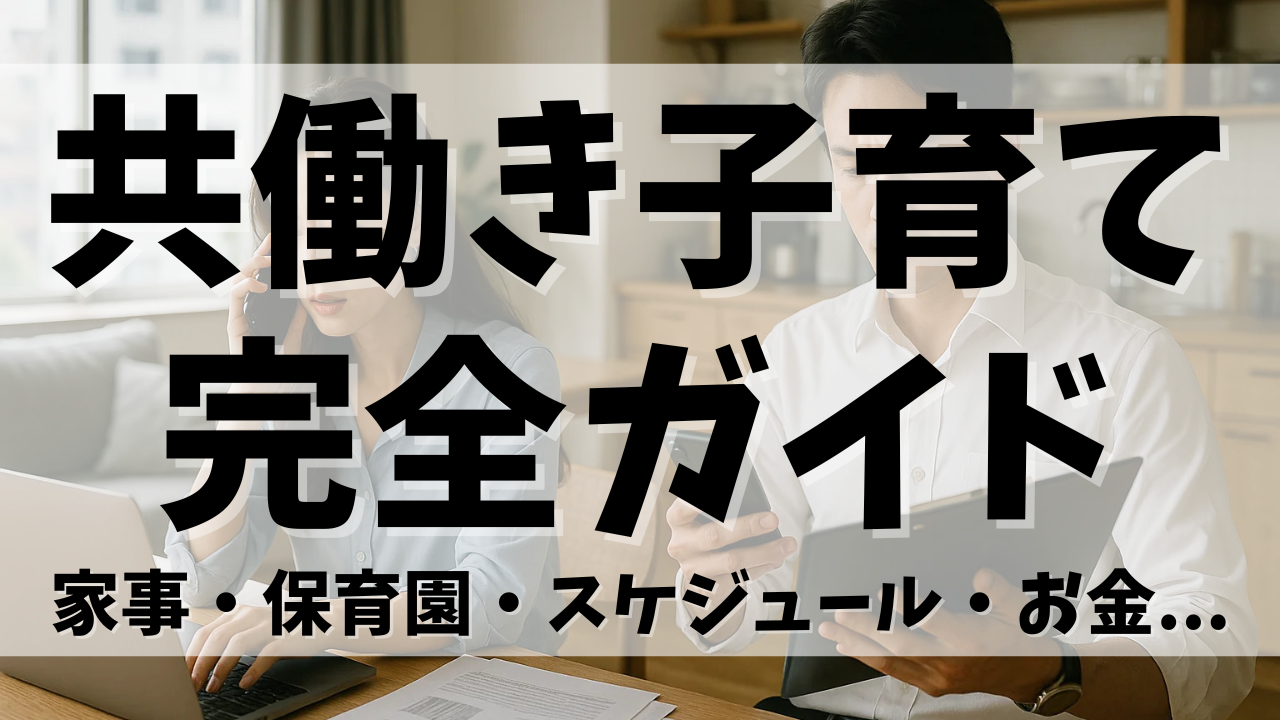
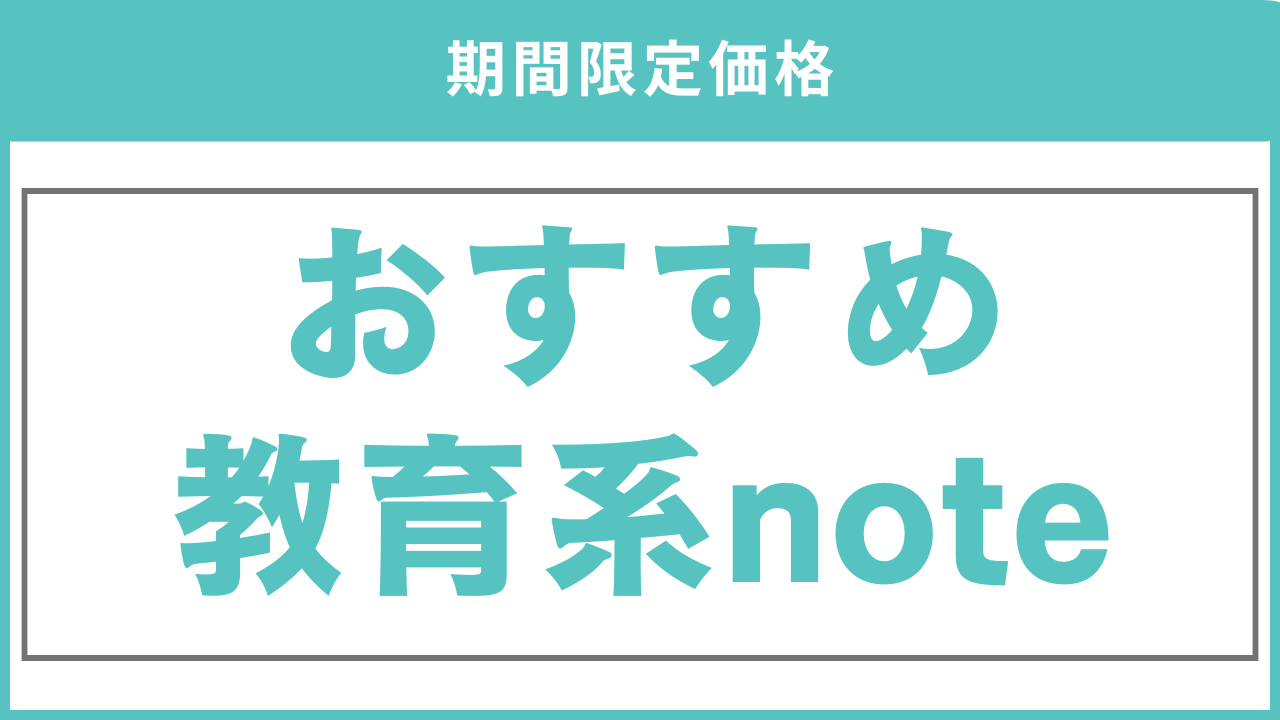


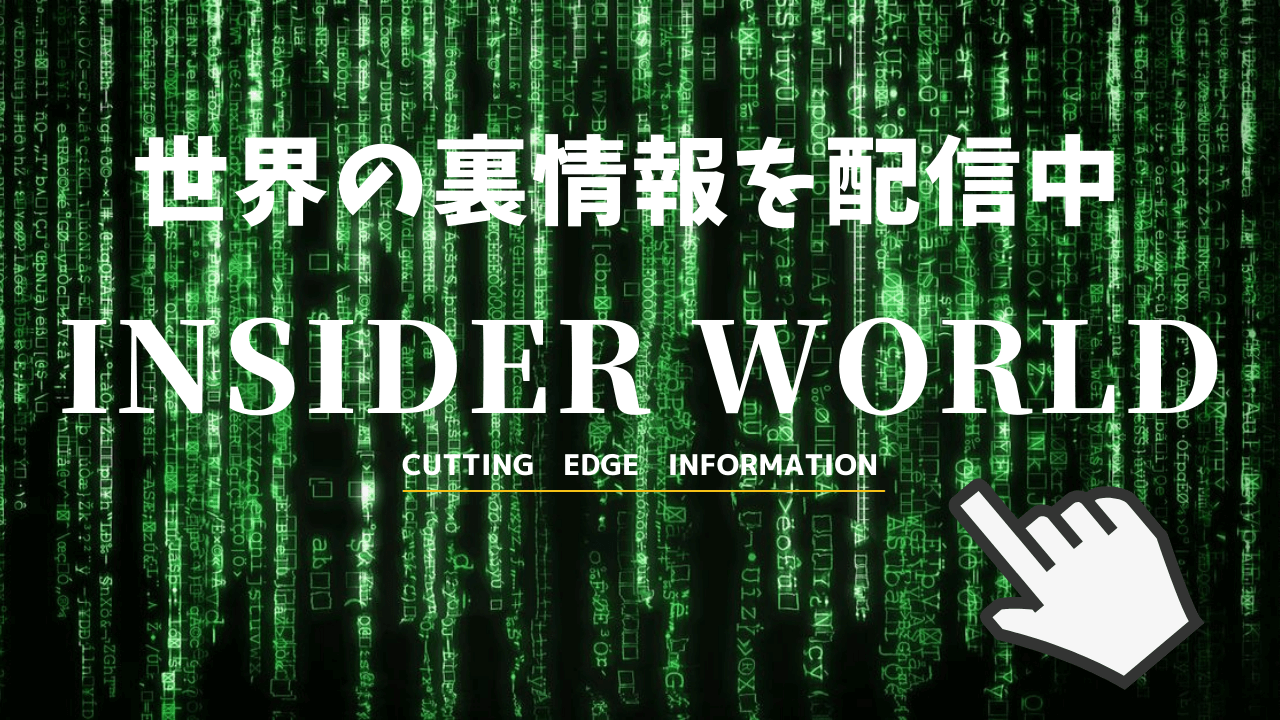


コメント